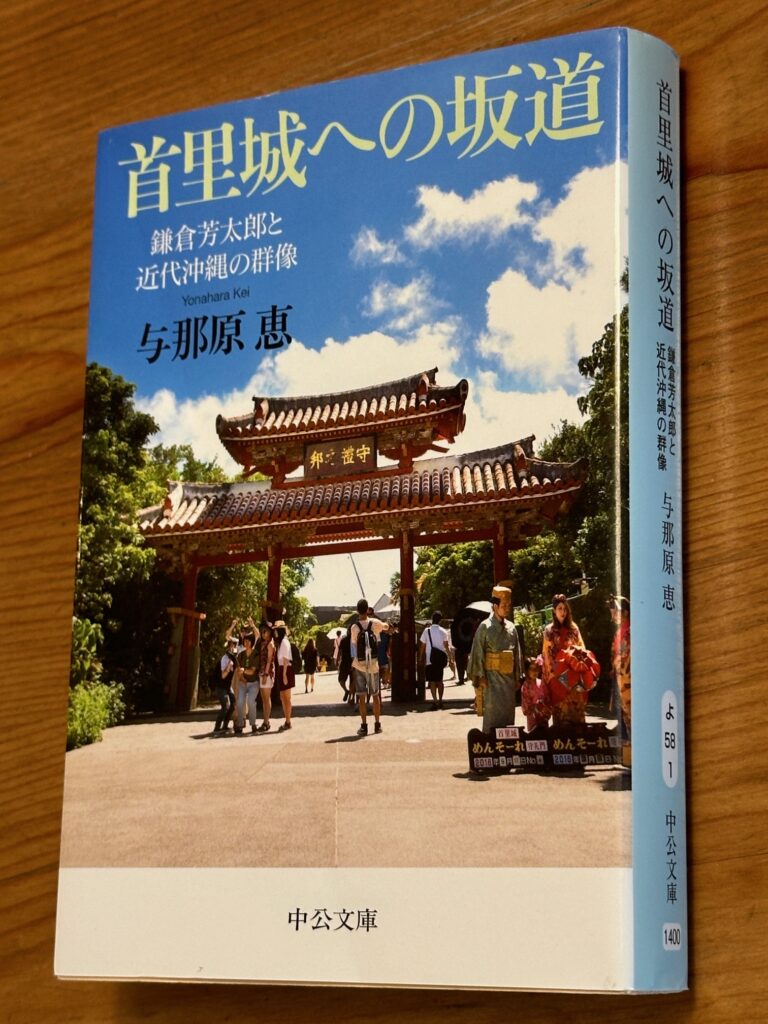おすすめ度:★★★★★ 入手容易さ:★★★★★ 読破容易さ:★★★★☆ 島ぁ度:★★★☆☆
[2013年7月 筑摩書房刊 2016年11月 中央公論新社(中公文庫)刊 ISBN978-4-12-206322-8]
手っ取り早く、裏表紙あらすじの引用で本書を紹介すると…
大正末期から昭和初期、大々的な琉球芸術調査を行い、貴重かつ膨大な資料を残した研究者・鎌倉芳太郎。稀代の記録者の仕事を紹介する本邦初の評伝であるとともに、彼に琉球文化の扉を開いた人々の姿、そしてそれが現代に繋がるまでの熱きドラマを描く。第二回河合隼雄学芸賞。第十四回石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞をダブル受賞。
与那原恵「首里城への道」中公文庫 裏表紙あらすじ
といった本だ。単行本の初版は、2013年7月に筑摩書房から発行されている。文庫本は2016年11月に中公文庫から発行されており、私はこちらを読んだ。
今、鎌倉芳太郎が残した資料をもとに復元された首里城が2020年に燃え尽き、再建の途上にある。本書は、ぜひとも、今また読み返されるべき本だ。
鎌倉芳太郎という人物の生涯を肩書で表すと、美術家で現在の東京藝術大学(美校)の教師、型絵染の研究者だったと言える。若き日に、芸術的な興味から、琉球王国の名残の残る戦前の沖縄を訪れ、その美に魅せられ、当時すでに失われつつあった琉球の美を残すべく研究にのめりこみ、広範に渡る琉球美術の膨大な記録を残した人物だ。鎌倉の沖縄研究は断続しながらも16年に渡ったというが、本書を通じて鎌倉の生涯を鑑みるに、それは若かりし頃の「いっときの間」ではなかったかと思う。「若さ」なくしては、きっと成しえない膨大なメモやスケッチ類、写真による記録。そして、この「若きパッション」によって記録された写真が、後にかけがえのない映像資料として甦ってくるのだ。
本書の第一章、冒頭では、琉球が琉球処分を経て沖縄縣となるまでの時代が短くまとめられ、そこから鎌倉芳太郎の生い立ち、大正前期の学校歴へとつながる。琉球美術に魅せられた人々と鎌倉との出会いがあり、その後の東京美術学校(美校、現・東京藝術大学)への道すじと琉球美術への関心、沖縄行きのストーリーが語られている。
美校の師範科を卒業した鎌倉は、大正十年に美術教師として沖縄にやってくる。光あふれる沖縄の風景に新鮮な魅力をおぼえ、当時すでに朽ちつつあった琉球王国の名残、建築物を見て回ったことや、下宿先であった首里の旧家、上層士族の末裔の屋敷に住まう日々の様子が語られている。そして第二章以降、沖縄学に目覚めた先駆者たちとの出会い、王国の美を支えた工芸職人たちとの交流や、取り壊しの憂き目に直面しつつあった首里城の保存運動に乗り出したことなどが、つぶさに語られ、第六章298ページの終わりまで、末吉麦門冬や比嘉朝健など、鎌倉とかかわりのあった沖縄のジャーナリストの先駆けたちとのエピソードや、琉球芸術の記録行、宮古島、八重山諸島への調査行についてが語られている。
私としては、第四章の写真技法の習得にかかる部分に特に興味がある。当時はガラス乾板の時代。デジカメはむろん、フィルムを使用するカメラもまだ出始めの時代だ。重く割れやすいガラスの感光板を携行し、蛇腹式の大型カメラで撮影するのだ。撮影は専門の「技術者」しかできない。鎌倉は、美校の写真科教授に、速成での写真術の教授を求める。鎌倉には写真撮影の経験はない。習得には「三年はかかる」と主張する教授を説き伏せた鎌倉は、なんと一週間で撮影技術を物にする。よほどの努力家であると同時に、写真科主任の森芳太郎教授の的を得た指導もすごいと言わざるを得ない。以下は、本書中に引用されている写真家木村伊兵衛の文だ。
大正年間に一学者の手で、技術的にも、記録的にもこれだけ完璧な写真が撮影されていたということは、まさに驚くべきことである。写真は本来、このようなドキュメントとしての役割こそが第一義のものであるわけだが、(略)どこまでも学者の目で克明に撮られたものであることに、また格別の価値がある。もちろん、当時としては最高のタゴールのレンズやイルフォードの乾板を用い、撮影にあたっては沖縄の強い太陽光線を十分に計算に入れ、影をうまく生かし、高い建物に対してはあおりの技術を使うなど、鎌倉芳太郎先生の写真家としての才能におどろかないわけにはいかないが、やはり、そうした技術の上に学術的なねらいが生かされたとうところに深い意味がある。(木村伊兵衛「魂のこもった貴重な写真展」昭和四十七年)
(木村伊兵衛「魂のこもった貴重な写真展」『50年前の沖縄』展リリース資料 サントリー美術館) 与那原恵「首里城への坂道」中公文庫 第四章 163-162ページ
鎌倉が東京の美校に戻り大戦期を経て、沖縄が日本復帰を迎えるまでに、鎌倉は73歳になっている。沖縄戦によって全てを焼かれてしまった事に心を痛めたためか、再び鎌倉が沖縄を訪れることは、沖縄の日本復帰の直前まで無かったという。486ページもある本書の半分以上が、鎌倉が沖縄に滞在し資料を収集した戦前期の物語だ。以降、本書の第七章からは、鎌倉や鎌倉をめぐる「沖縄学」の人物たちの東京での活動、鎌倉の紅型研究、そして、戦前に鎌倉らが撮影した琉球美術のガラス乾板の公開への軌跡が記されている。鎌倉の晩年の話だ。
大正末から昭和初期にかけて撮影したガラス乾板の写真は、琉球芸術調査を終えた直後に東京美術学校の展覧会で展示したり、『世界美術全集』(昭和二年)や『南海古陶瓷』(昭和十一年)に紹介したりしたが、そののち戦争の時代になり、琉球芸術を紹介する機会は失われてしまった。戦中、防空壕のなかに茶箱に詰めたガラス乾板を守りつづけたものの、それを開ける機会さえなかった。 ー中略ー 戦後は紅型研究と型絵染制作に没頭していたので、写真をかえりみる余裕もなかったのだろう。
与那原恵「首里城への坂道」中公文庫 第九章 399-400ページ
千数百点のガラス乾板の存在を明かしたのが、日本古美術展の講演だったのか、滞在中におこなわれたべつの講演だったのか、さだかではないと吉澤はいうが、鎌倉がそれを語った瞬間は鮮明に記憶していた。
「沖縄のすべてが灰燼に帰し、写真一枚ないといわれるが、五十年前に撮っているとおっしゃるのです。首里城をはじめとする文化財、八重山、宮古の風景、工芸品、それからまぼろしとなっていた御後絵(おごえ/ルビ)も撮影している、と。その会場にいた沖縄の新聞記者たちから、うわーっというどよめきの声があがったことをはっきりとおぼえています」
上の引用は、初めて沖縄を訪れてから50年後、日本復帰前年の春に、再び沖縄を鎌倉が訪れた際、鎌倉をアテンドしたという吉澤氏の言葉の部分だ。そこから、沖縄の日本復帰の年に、東京と沖縄の両方で催された写真展「50年前の沖縄」が生まれた。幼かった私も、これらの写真の多くを沖縄県立博物館で目にしている。
このように、鎌倉芳太郎の軌跡を克明に綴った本書であるが、私の興味は本書の主題のほかにもある。それは「著者」のことだ。
著者の与那原恵さんは、ご両親が沖縄から本土に出てきて本土で生まれ育ったという。私たちが言うところの、いわゆる「二世」だ。だからだろうか、うちなんちゅではない本土から来た大エリートである鎌倉芳太郎を本書で見事に明晰に描き切っている。しかし、一方ではその文体は優しい感情に満ちている。
一般的に、著者の母語である方言やなまりは文体にも表れるものだ。例えば、本ブログで別に取り上げた金城芳子先生の「なはをんな一代記」などは、「ネイティブ・オキナワン」の私の頭の中では、見事に沖縄のオバアの語り口、抑揚やアクセントが再現され鳴り響く。感情がダイレクトに心に入りこんでくる文体だ。語り口がそのまま文章となって表れるタイプの著者の場合がきっとそうなのだろう。しかし、文才に恵まれ職業的なスキルを身につけた書き手の場合はまた違う。本書がそうなのだと思う。本書の文体は、知的で緻密でありながら平易で読みやすい。プロの、エリートの書き手の文体だ。優れたNHKアナウンサーによるドキュメンタリーのナレーションが頭の中で語りゆく感じだ。ただ、その底には、何かの「魂」が宿っているように感じられてならなかった。そこに優しさを感じるのだ。その「魂」とは何なのだろう。
もちろん、上記で紹介した本文も大変面白く興味深いのだが、私が敢えてここで取り上げたいのは「あとがき」のほう。単行本として発行された2013年6月の「あとがき」である。与那原恵さんが、本書の主役である鎌倉芳太郎のことを初めて知ったくだりに、与那原恵さんのお父様のことが書かれている。わずか8ページのうちに、お父様とお母様が沖縄で生まれ戦前の東京で住むことになった経緯や、与那原恵さんがご自身のルーツである沖縄に興味を持ち、何度も訪れることになった様子が短く記されている。本文の長大で克明な鎌倉芳太郎の評伝を読み終わったあと、この「あとがき」に接して実にほっとした。「この人もウチナーンチュなんだ」と。それがおそらく「魂」の正体なのだろうと、ここで得心がいったのだ。
本土で暮らしてみてわかるのが、様々な境遇で沖縄から出てきた沖縄人がいることである。そして大体の場合、その子供がいることになる。うちには小学生の男の子が一人いる。私自身は二十歳で東京に出てきた「一世」だが、私の子はその呼び方に則ると「二世」ということになる。そして、年齢的な世代は私とははるかに異なるが、おなじ「一世」である私の知人にカメラマンの石川文洋さんがいる。文洋さんには「二世」の男のお子さん(といっても私とほぼ同世代)がいる。ある日、文洋さんから突然電話がかかってきて、お互いの「二世」の沖縄への興味、関わりについて話すことがあった。息子さんは東京におられるとのことだが、文洋さんが沖縄の事を想われているのとは、また温度が違う。君のところはどうだ…といったようなことがその時の話題だったと記憶している。
沖縄と本土との距離感は、私が上京してきた頃(1985年)と文洋さんの時代では大きな違いがあった。私が上京する十数年前までは、まだ一般に沖縄への特別感、差別などが普通にあったという。私が学生の頃にはもう、ほとんど感じることはなかったが、社会に出てはじめて、そのような違和感の名残に直面することがしばしばあった。それを感じさせる世代(私から二回りほど年上の人々)からわかるのは、おそらく1972年5月15日の日本復帰がその潮目であっただろうということだ。その日、私は小学2年生で、私はいわゆる「復帰世代」でもあるが、本土で暗い日常を味わった青年(先輩)たちのことも良く見知っていた。その後、沖縄のイメージが明るく美しいものに変わってきたことは大きな幸せだ。私たちは良い時代に沖縄から出てくることができた。
そして、LCCやインターネット、ラジコなどのおかげで、どこに居てもつねに沖縄と平常的につながっていられる今の時代のことを勘定に入れると、実は私などは「0.5世」といえるかもしれない。いや、むしろ「一世」だの「二世」だのゴチャゴチャ言っている場合ではないのかもしれない。「二世」の想う沖縄はきっとこんな程度だ、と断定などできない時代に入っていると感じる。与那原恵さんのような存在には脱帽だ。そのマインドといい機動力、取材力といい、心から尊敬したい。
この本のAmazonでのご購入はこちらから… (アフィリエイトプログラムに参加しています)